カテーテル治療とは
実際の治療ではカテーテル治療と言って、腕や足の血管から動脈の血管の中を伝って細い管を持っていって詰まりかけている血管を広げる治療をします。
実際にそういった治療をされた方からよく聞かれることがあります。
「狭心症になっちゃったけど、安静にしてた方がいいよね」
「今まで通り動いちゃいけないよね」
「普段通り生活できるんだろうか?」
こういった不安をよく聞きます。そういった方によくお話しするのは、ぜひ体を動かしてください。
今まで通り基本的に過ごすことは可能です。
カテーテル治療後の注意点
カテーテル治療が終わったあと、あなたは主治医から「手術はうまくいきました」と説明を受けます。
そしてあなた自身も症状がなくなって、説明を受けてほっとしてると思います。一緒に説明を聞かれたご家族もほっとしてることでしょう。
日本のカテーテル治療のレベルは、世界でもトップレベルです。
こういった環境で治療を受けれるのは非常にありがたいことだと思います。ただ狭心症になったから、運動は控えるべきか、これまでのような生活ができなくなっちゃうんじゃないかこういった心配をされる方が多いですが、決してそんなことはありません。
運動はぜひ行ってください。
しかし、無事に手術が終わったので、良かったということで全てが解決したわけではありません。
注意したいこと
◯再狭窄のリスク
どんな名医が治療しても、治療後の再狭窄(これは再び病状が悪化して狭心症の症状が出ること)のリスクはゼロにはなりません。決められた薬を毎日服用しましょう。
そして、また狭心症を疑うような症状が出た時には主人に早めに相談しましょう。我慢するのは良くないです。
◯原因疾患の対策が必要
動脈硬化の漸進の結果としての原因となるものがあったはずです。基本的には動脈硬化は全身に起こりますので、今回治療しなかった場所にも必ずある程度の動脈硬化があります。
そして今後、狭心症が起きる可能性もあります。また頚動脈(首の血管)や足の血管など、全身の血管でそういった病変が進行しないように狭心症や心筋梗塞の原因となる血圧やコレステロールの管理、血糖値が高くならないようにする、喫煙する、こういったことに向き合っていくことが重要になります。
これから先、動脈硬化の進行を防ぎ、動脈硬化の原因となる高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙に対して治療や対策を取ることで動脈硬化の進展を少しでも抑えましょう。
そのためには生活習慣の見直しと適度な運動と食生活を整えること、これらが大事になります。
治療後に行う検査
◯カテーテル検査
冠動脈造影検査は多くのところで治療から6ヶ月から10ヶ月の間で確認の検査をすることが多いです。
治療した場所に再狭窄がないか確認します。その中でも約1割に再狭窄が見つかり、必要に応じて再治療することがあります。この確認の検査で再狭窄がなければ、その後は定期的にカテーテル検査することは基本的にありません。毎年検査するようなことは一般的にはありません。この確認の検査も最近では、CTで代わりに行う施設も増えてきてます。今では造影剤を用いてCTでも血管の中をしっかり映すことができます。
◯運動負荷心電図
胸痛がはっきり自覚症状としてなくても、狭心症になっていることがあるので、こちらを見るために運動負荷をかけて検査をすることが発見につながることがあります。治療に用いるステントと言われる金属性の筒があるんですが、薬剤溶質性ステントというものを最近ではよく使われます。
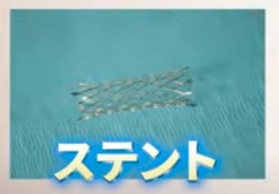
以前は3割ぐらいの方が再狭窄また治療が必要になる方が多かったのですが、ステントに薬が塗ってあって再狭窄を予防するような薬こういった薬が塗ってあるため、ステントの部分の再狭窄はかなり減っています。
ただ逆に言うと、薬が塗ってあるためステントは金属でできているので、そのまま体内にあると異物と判断して血栓がついたり、膜が張ってきたりします。
逆に薬が塗ってあることで安定した状態になるまで時間かかることがあります。剥き出しの金属は血栓が詰まる血栓症のリスクもありますので、それを予防するために、抗血小板薬と言って血をサラサラにする薬が一定期間必要になります。
特に一定期間は2種類の抗血小板薬を継続し、半年〜10ヶ月で行う確認造影で問題ないこと確認するまでは2剤を使って、その後1剤に減ることが多いです。
ステント血栓症とは
血栓で完全に詰まってしまう心筋梗塞を起こす場合もみられます。こういったことは治療してから3ヶ月以内に起こりやすいと言われてます。
なのでその間は特にその2剤の抗血小板薬が非常に大事になります。時間が経ってから1剤にはなりますが、この薬は継続することによって再狭窄、ステント血栓症を予防するのに役立ちます。ステントもだんだん改良されてきて再狭窄は減ってきていますが、まだゼロにはやはりなりません。
今後も治療の仕方が改善され、ステントも改善されてこういったことが減ることを望んでいます。
ただ抗血小板薬は血をサラサラにする薬なので逆に出血するリスクが増えます。
特に心配なのが胃潰瘍などの消化管出血です。こちらの予防のために特に2剤の抗血小板薬を飲んでいる間は胃潰瘍の予防の薬も併用することが実際には多いです。
まとめ
今回は狭心症の治療の後、治療がうまくいった場合には基本、日常生活に制限は特にありません。ただ注意することもあります。
- 抗血小板薬、血をサラサラにする薬は継続が必要であること
- 定期的に通院して、悪化してないか主治医と相談すること
- 適度な運動や食生活を気をつけて動脈硬化につながる生活習慣を見直すこと
上記が大事になります。
こういったことに気をつけていけば、以前と同じような生活が十分遅れますのでご安心ください。









